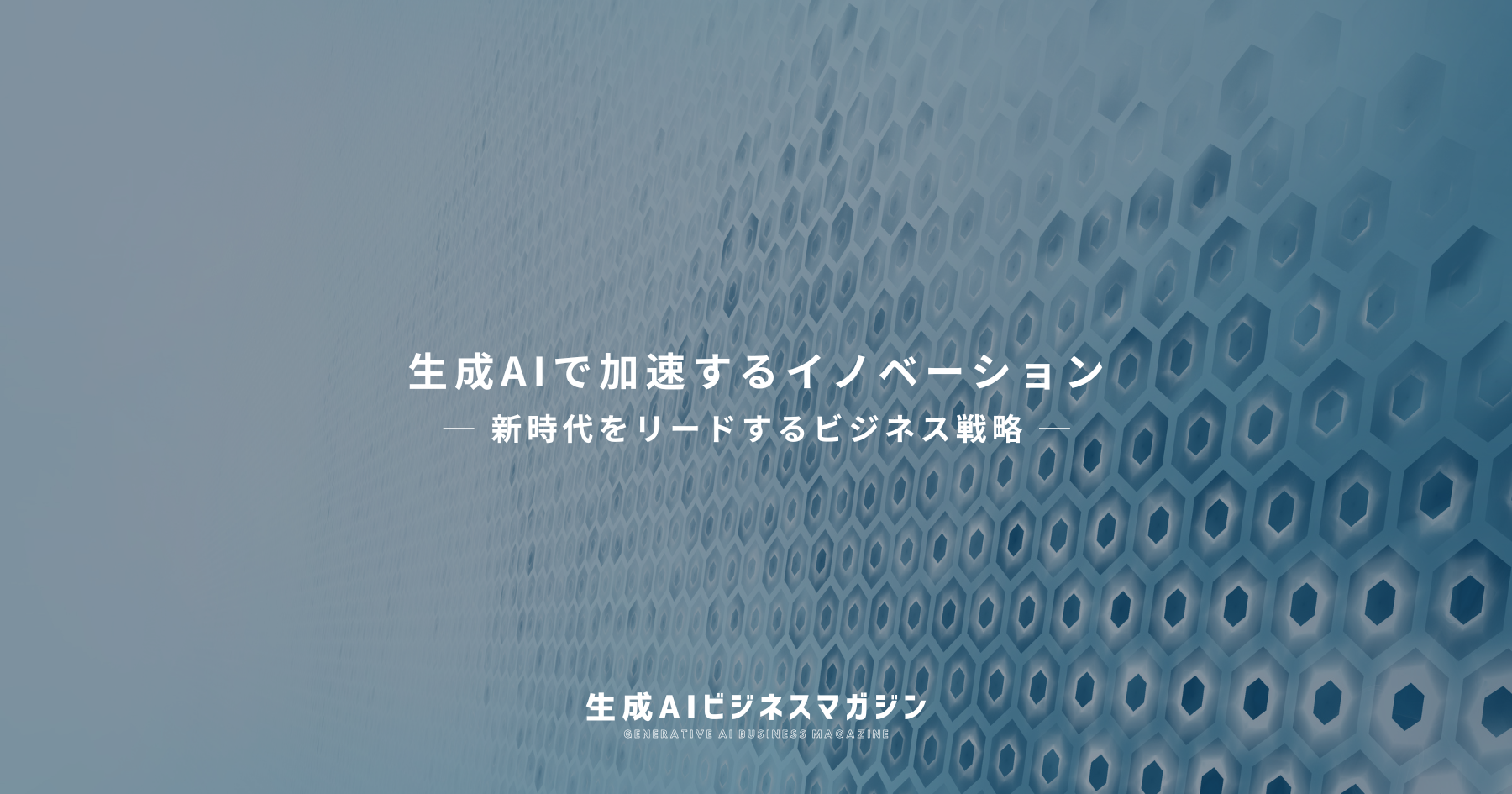スマホで「おはよう」と入力すると、「今日も一日頑張りましょう!」と自動で予測変換されるような時代。自分の気持ちを先読みされて「ちょっと気持ち悪いな」と思いつつも、便利だからと使っている人も多いのではないでしょうか。
実はこれ、AIの力なんです。でも、そんな身近なAIの話とは別に、世界では今、もっと大きな「AI革命」が静かに、そして猛スピードで進行しています。
「AGI(人工汎用知能)」という言葉を聞いたことがありますか? 簡単に言えば「人間より賢いAI」のこと。ほんの数年前まではSFの世界の話だと思われていましたが、今や「2030年より前に実現する」と言われています。アメリカのバイデン政権でAI担当特別顧問を務めたベン・ブキャナン氏に至っては「あと2〜3年でAGIが来る」と発言しているほど。
そして、この状況に日本は完全に置いてけぼりを食らっています。このコラムでは、なぜ日本はAI後進国になってしまったのか、そしてその先にある危機について考えていきましょう。
世界のAI戦争はすでに始まっている
AI開発の最前線では、アメリカと中国が「先にAGIを手に入れるのはどっちだ」と熾烈な開発競争を繰り広げています。
この競争、単に「儲かるから」というビジネス的な理由だけではありません。日本大学の小谷賢教授によれば、両国にとってAIは「経済以上に安全保障上の問題」なのです。
アメリカにとって負けることは「自由と民主主義の敗北」を意味し、中国にとっては「共産党独裁の正当性の崩壊」を意味します。どちらも国の根幹に関わる問題なので、絶対に負けられない。それが彼らがAI開発に全力を注ぐ理由です。
一方、日本は「AIで経済的にどう儲けるか」という次元の話で終わっていることが多く、「国家の生き残り」という視点が決定的に欠けています。
日本の「丸腰」ぶりが露呈する防衛分野
特に安全保障の分野での日本のAI活用は、世界から大きく遅れています。
アメリカでは、国防総省が2017年に「プロジェクト・メイブン」という軍用AI活用プロジェクトを立ち上げ、Google、Amazon、Microsoft、Palantirなど超一流のテック企業が参画しています。
これは「国が資金を出して、民間企業によるAI研究を促す取り組み」です。日本の防衛省も同様の試みを行ってはいるものの、「国の命令に従って軍事研究をやるなんてとんでもない」という空気が根強く、ほとんど進展していないのが現状です。
「ちょっと待って、平和国家の日本が軍事目的でAIを使うなんて、それこそ問題じゃない?」と思われるかもしれません。でも実際には、AIの軍事利用を避けるという選択肢は、世界情勢の中でもはや現実的ではなくなっています。
足元に迫る危機:サイバー攻撃から国民の生活を守れるか
AIの活用が最も急がれるのは、サイバー攻撃への対応です。
2024年12月から2025年1月にかけて、日本航空(JAL)への攻撃をはじめ、日本が複数回にわたってサイバー攻撃を受けたことは記憶に新しいでしょう。これまでは「日本語」という言語の壁があったため、海外からの攻撃は比較的少なかったのですが、AIの発達によってその壁は簡単に乗り越えられるようになりました。
サイバー攻撃とは、コンピュータシステムの弱点(脆弱性)を見つけて突くことで不正侵入する行為です。AIが賢くなればなるほど、そうした弱点を発見する精度は高まります。
一方で、攻撃を受ける側も、AIを使ってより安全なコードを書いたり、侵入検知を強化したりできるようになります。つまり、「強力なAIによるサイバー攻撃を防ぐには、強力なAIによる防御が不可欠」なのです。
しかし日本では、サイバー攻撃に対して「攻撃されてから対応する」という受け身の姿勢(「アクティブサイバーディフェンス」)しか法的に認められていません。これは世界標準から見ても「常識外れ」の対応と言わざるを得ません。
台湾有事:AIが描き出す最悪のシナリオ
日本のAI対応の遅れがもたらす「最悪のシナリオ」として、小谷教授は台湾有事の際の混乱を指摘しています。
実際の武力衝突が起きる前に、「米軍に加担して台湾有事に介入すれば、日本にも核ミサイルが撃ち込まれる」といった偽情報が日本中に拡散される可能性があります。AI技術の発達により、こうした偽情報はますます精巧になり、見分けがつかなくなっています。
それと同時にサイバー攻撃も仕掛けられれば、国内は大混乱に陥り、世論もバラバラになるでしょう。そうなると国としての意思決定さえ難しくなり、「あたふたしているうちに、同盟国であるアメリカにも見捨てられる」という事態も十分に考えられます。
日本政府の「テクノロジー音痴」問題
なぜ日本はここまでAI後進国になってしまったのでしょうか。その根本的な理由の一つに、「技術がわかる理系の人材が政府内にほとんどいない」という問題があります。
政治家も官僚も多くが法学部出身で、テクノロジーの本質的な理解に欠けています。一方、アメリカでは「リボルビングドア」と呼ばれる制度があり、政治家、実業家、研究者が様々な立場を行き来しています。これにより、最先端の技術知識が政策決定に活かされているのです。
日本の防衛省が「何年間も中国からハッキングされていたことに気づかず、アメリカに指摘されて初めて知った」というエピソードは、日本政府の「テクノロジー音痴ぶり」を象徴しています。
私たちにできること:AI後進国からの脱却への道
ここまで読むと「もう手遅れなのでは?」と思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。日本がAI後進国から抜け出すために、私たち一人ひとりができることがあります。
まず、AI技術に対する正しい理解を深めることです。「AIは単なる便利なツール」ではなく、「国の未来を左右する重要技術」だという認識を持つことが大切です。
次に、政府や企業に対して、AIの安全保障面での活用を促す声を上げることです。特に「技術と政策の両方を理解できる人材の育成・登用」を求めていくことが重要でしょう。
そして何より、私たち自身がAIリテラシーを高め、次世代にもそれを伝えていくことです。中学生や高校生の段階から、AIの本質や可能性、そして危険性についても学ぶ機会を増やしていくべきでしょう。
世界はすでに「AIが国の未来を決める時代」に突入しています。AIは単に「お金を稼ぐツール」ではなく、「国の力そのもの」になりつつあるのです。
デジタルツインと呼ばれる技術で現実世界を再現し、AIが最適な行動パターンを事前に学習することで、チェスの名人が何手も先を読むように、様々な状況に対応できるようになっています。これは、従来の軍事力とは根本的に異なる「実効支配力」を国家にもたらします。
日本は残念ながら、技術がわかる人が政策を決める場所にいないうえに、安全保障技術への投資も足りず、二重のハンデを負っています。今の日本は「靴も履かずに荒野に立っている」ような状態。このギャップを埋めるための行動を、今すぐ始めなければなりません。
私たちの未来は、私たち自身の手で作り上げるものです。AI後進国からの脱却は、国の存続にかかわる重要な課題であることを、一人でも多くの日本人が認識することから始まるのではないでしょうか。
このサイトでは、AI技術を活用した情報収集・要約及び解説、執筆をもとに、編集チームが編集を行っています。AIによるデータ処理と生成、人間の視点を組み合わせ、わかりやすく役立つ情報をお届けすることに努めてまいります。※AIによる生成コンテンツには誤りが含まれる可能性があるため、情報の正確性を確保するために最善を尽くします。