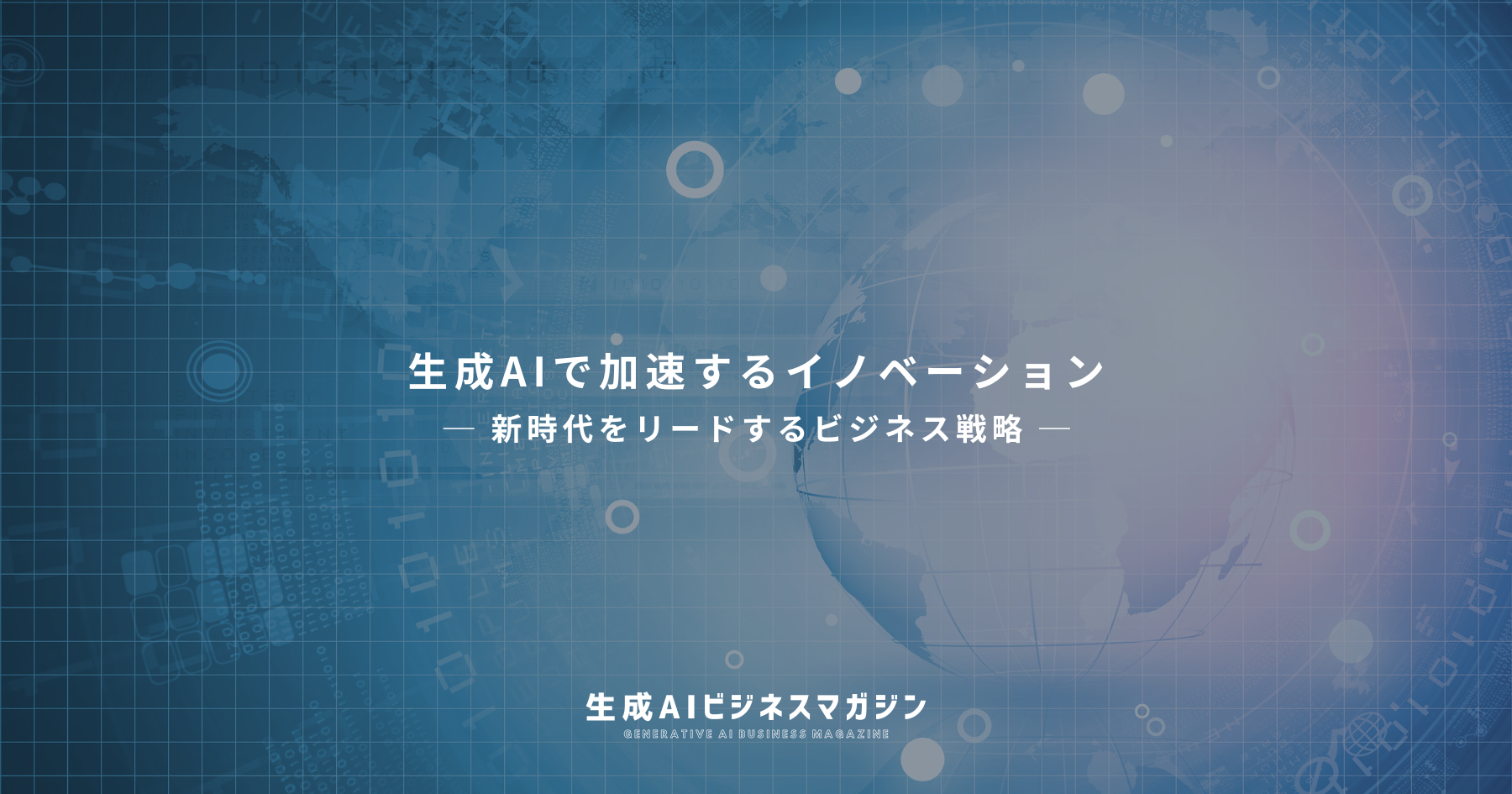春になると、フレッシュな新人さんたちが職場にやってきますよね。でも今年は何かが違う。パソコンを開くなり「ChatGPTで資料のたたき台作りますね」なんて言い出す子がいて、「え、それってアリなの?」と戸惑った方も多いのではないでしょうか。
実は、彼らは生成AIと一緒に大学生活を過ごしてきた「AI世代」。レポートも履歴書も、AIをフル活用して作ってきた世代なんです。そんな彼らを前に、従来の指導方法が通用しなくなってきているのが現実。今回は、AI世代の部下との上手な付き合い方について、現場の声を交えながら考えてみましょう。
なぜ若手は手作業を嫌がるのか?「デジタル摩擦」の正体
「最近の若い子は根気がない」なんて思っていませんか?でも、彼らの気持ちを理解するには、まず「デジタル摩擦」という現象を知る必要があります。
AIなら30秒で終わる資料作成を、「修業だから」と言って3時間かけて手作業でやらされる。彼らにとってこれは、電卓があるのにそろばんで計算させられるような感覚なんです。「なんで効率の悪いことをわざわざ?」という疑問が湧くのは当然ですよね。
グロービスの鳥潟幸志氏によると、AI世代の若手はAIを「第二の脳」として捉えているそうです。便利なツールを使ってサボっているわけではなく、自分の能力を拡張させるパートナーとしてAIを活用している。つまり、AIを使うことが彼らにとっての「普通」なんです。
考えてみれば、私たちだって電卓やエクセルを使うのは当たり前。AIもそれと同じツールの延長線上にあると思えば、納得できるのではないでしょうか。
「修業」の形が変わった!AI時代の人材育成術
「パワポをうまく作れる人は偉くなる」なんて時代がありましたよね。資料作成を通じて、情報の整理力やプレゼン力を身につけるのが定番の修業でした。でも今は、スライド作成はAIの得意分野。じゃあ、若手はどこで成長すればいいのでしょう?
ここで重要なのが「AI込みでの修業」という考え方です。イーデザイン損保の元社長で、現在はAI活用支援を行う桑原茂雄氏は、こんな経験を語っています。
AIに資料作りを任せるようになってから、本当に伝えたい情報だけを整理してAIに指示するスキルが磨かれたそうです。見た目は前よりシンプルになったけれど、相手に要点が伝わりやすくなった。つまり、AIを使うことで「本質を見抜く力」が鍛えられたんです。
でも、100%AIに任せた成果物は、やっぱり物足りない。だからこそ、AIが出してきたものに自分らしい「味付け」を加える感性を磨くことが、新しい修業になるわけです。
例えば、AIが作った箇条書きの企画書に対して「この相手にはもう少し感情に訴える表現を入れた方がいいかも」とか「ここは具体例があった方が伝わりそう」といった調整ができるようになること。これって、実はとても高度なコミュニケーション能力ですよね。
中間管理職が「罰ゲーム」から解放される日
「中間管理職は罰ゲーム」なんて言葉を聞いたことありませんか?上からのプレッシャーと下からの突き上げに挟まれて、煩雑な業務に追われる毎日。でも、AIの力を借りれば、この状況も変わりそうです。
リンクアンドモチベーションの藤田理孝氏は、まずはメンバーのコンディションチェックからAIに任せていけばいいと提案しています。勤怠情報や日報をもとに、メンバーに異変があればアラートが立つ仕組み。これなら、わざわざ新しい作業を増やすことなく、効率的に部下の状況を把握できます。
面白いのは、AIを使った「フィードバックボット」の話。藤田氏は自分のフィードバックを30個ほどピックアップして、「藤田らしいアドバイスをするボット」を作ったそうです。すると、部下からは「先にAIに相談したほうが、何度も怒られずに済む」と好評だとか。
これって、実はwin-winの関係なんです。部下は気軽に相談できるし、上司は同じことを何度も言わなくて済む。そして本当に重要な場面で、人間同士のコミュニケーションに時間を使えるようになるんです。
さよなら、マイクロマネジメント!新時代のリーダーシップ
「細かく指示を出して管理する」という昭和スタイルのマネジメントが、いよいよ終わりを迎えています。部下がAIを使いこなす時代に、上司が細かい手法まで指示するのはナンセンス。むしろ、「なぜこれをやるのか」という目的や、「これだけは守って」という枠組みを明確に伝えることが重要になってきます。
AICX協会代表の小澤健祐氏(おざけん)によると、若手は「深さ」に走りがちだそうです。一つのことを掘り下げるのは得意だけど、全体を俯瞰したり、時間軸で考えたりするのは苦手。
そこでマネジャーに求められるのは、彼らに足りない「広さ」「構造」「時間」の視点を提供すること。例えば、「営業的にはいいアイデアだけど、サポート部門の立場ならどう思う?」とか「シェアを取ることより、利益率を重視すべきじゃない?」といった「いい問い」を投げかけることです。
これって、実は部下を信頼しているからこそできること。細かく管理するのではなく、考える材料を与えて自分で判断させる。そんなマネジメントスタイルが求められているんです。
「名選手、必ずしも名監督ならず」がAIで明らかに
従来は、プレイヤーとして優秀だった人が管理職になるのが普通でした。でも「名選手必ずしも名監督ならず」という言葉があるように、プレイイング能力とマネジメント能力は別物。そして今、AIの力で「ホンモノの管理能力」が可視化され始めています。
インディードリクルートパートナーズの高田悠矢氏は、「一見複雑そうだが、実は単純な業務」がAIに代替されることで、元「名プレイヤー」の仮面が剥がされる可能性を指摘しています。データ集計や資料作成といった「実は単純な業務」で価値を示してきた管理職は、いよいよ変化を求められる時代になったんです。
興味深いのは、エンゲージメント向上支援を手がけるU-ZEROが開発中の「EVダッシュボード」という仕組み。パルスサーベイ(部門メンバーのストレスややりがい)、チームシナジー(他部門からの評価)、ウェルビーイングスコア(総合的な心身の状態)といった指標を数値化して、管理職のコンピテンシーをスコアリングするそうです。
これまで定性的にしか評価できなかった「部下思いの上司」や「チームワークを大切にするリーダー」といった要素が、数字で見えるようになる。一見KPIが良くても、部下が成長していない、チームの雰囲気が悪い、他部門に迷惑をかけている──そんな管理職は「峻別」される時代が来るかもしれません。
会社の垣根を超えた「ドリームチーム」作り
最後に、とても興味深い変化をご紹介しましょう。AIの力を借りることで、会社の垣根を越えたチーム組成が可能になりつつあるんです。
リクルートワークス研究所の武藤久美子氏によると、「この仕事にはどういうスキルを持った人が必要か」「社内外を含めてどんな人材がいるか」をAIが把握できるようになってきたそうです。従来は所属メンバーという固定的なチームを率いるのが前提でしたが、今後はプロジェクトの成果軸で様々な人を集められるようになる。
ただし、スキルと専門性で人を集めても、その人たちに「この人と働きたい」と思ってもらえるかは別問題。「あなたの組織で、あなたのために自分のスキルを使いたい」と言ってもらえるような魅力的なリーダーになることが、これまで以上に重要になってきます。
スキルだけで評価されているような感覚に陥りがちな時代だからこそ、メンバーが生き生きと働けるような場づくりや、人間関係の構築といった「人間らしい」要素が、マネジャーの差別化ポイントになるんです。
まとめ:AI時代のマネジャーは「人間らしさ」が武器
AI世代の部下たちは、私たちが思っている以上に優秀で、効率的で、可能性に満ちています。彼らのAI活用を「ズル」と捉えるのではなく、「新しい働き方」として受け入れることから始めてみませんか?
そして何より大切なのは、AIが得意な作業はAIに任せて、私たち人間にしかできない「共感」「創造」「判断」に時間と労力を投資すること。部下の成長を見守り、チームの雰囲気を良くし、メンバーが「この人のために頑張りたい」と思えるような関係性を築く──そんな「人間らしい」マネジメントが、AI時代の最強の武器になるはずです。
変化は怖いものですが、新しい時代の扉を開くチャンスでもあります。AI世代の部下たちと一緒に、これまでにない素晴らしいチームを作っていきましょう!
参考:NewsPicks「職場激震」AI世代の部下ができた。さて、どう育てる?(藤田美菜子氏)
このサイトでは、AI技術を活用した情報収集・要約及び解説、執筆をもとに、編集チームが編集を行っています。AIによるデータ処理と生成、人間の視点を組み合わせ、わかりやすく役立つ情報をお届けすることに努めてまいります。※AIによる生成コンテンツには誤りが含まれる可能性があるため、情報の正確性を確保するために最善を尽くします。